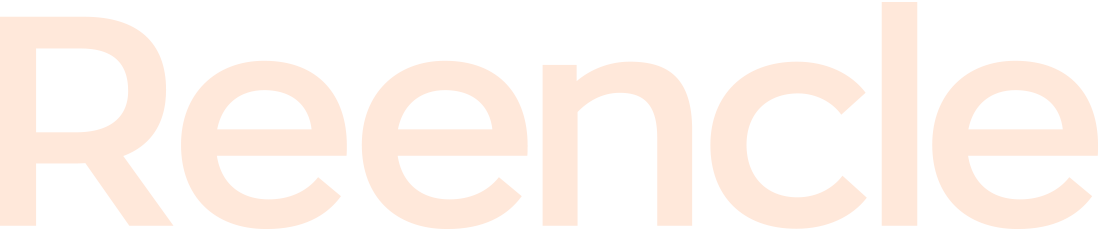Reencleを使えば「自前の微生物入り土壌改良資材」が無料で手に入る!

こんにちは!今回は家庭菜園や畑をされていらっしゃる皆さんに超朗報なお知らせがあります。
一般的な生ごみ処理機の処理物・副産物は乾燥されただけで作物・土壌にとって悪影響になる可能性が高いです。しかし、Reencle(リンクル)は凄いパワーを持っています。実はReencle、生ごみを堆肥化した“副産物”を、微生物入り土壌改良資材として使えることが公表できるようになりました。
いままで家庭菜園や畑をされる際に「有機肥料」や「土壌改良資材」などを購入されていた方が多かったと思いますが、Reencleから生まれる副産物を活用いただくことにより、自前の微生物入り土壌改良資材が無料で手に入ります。
雑草や枯れ葉などの残渣処理、防虫効果、作物の成長促進に非常に効果がありますので、気になる方は是非最後までご覧ください。今回はその仕組みや活用法を詳しくご紹介します。
■ 土壌改良資材って何? 〜種類と肥料との違い〜

土壌改良材とは、一言でいえば土を元気にする材料です。植物が育つためには適度な栄養と微生物、フカフカとした土壌構造が重要。そこをサポートするのが土壌改良資材の役割です。
●土壌改良資材の種類
ひとくちに「土壌改良材」といっても、含まれる成分や目的によってさまざまな種類があります。大きく分けると、下記のようなカテゴリーに分類できます。
●肥料との違い
肥料は“直接の栄養補給”、改良材は“土の体質改善”が主な目的になります。
●土壌改良資材の中で「微生物入り資材」は特に注目
・バーミキュライトなどの鉱物系改良材は、通気性や排水性を向上させるのに便利です。
・家畜糞堆肥や落ち葉堆肥などの有機改良材は、土壌に有機物を補給し、微生物相の活性を助けます。
・カルスNC-RやReencle副産物のような「微生物入り有機改良材」は、土壌の生物面を大幅に強化に繋がります。
とくに家庭菜園や小規模農業では、土壌改良資材をうまく選んで使うことで、化学肥料に頼らず健康的に作物を育てられるメリットがあります。その微生物入り土壌改良資材をReencleは無料で作ることができるというわけです。
■ Reencleの副産物ってどんなもの? 〜成分の秘密〜

■ どんなゴミを投入するのがベスト? 〜オススメ投入リスト〜
Reencleは「ゴミ」を処理し生活を快適にするのがメインの役割です。しかし、上質な堆肥・土壌改良資材を作ろうと思った場合は、投入するゴミに注意が必要です。あくまでも「上質な堆肥・土壌改良資材」を作りたい場合に限りますので、普段使いをされたい場合は気にせず色々なゴミを投入いただいて問題ありません。

※逆に注意したい食材

■ Reencle副産物が土にいい理由 〜ポイントを深掘り〜

■ もっと効果をアップするためのコツ

■ まとめ:生ごみを資源に変えて、土を元気に!
・Reencleを使えば、生ごみが堆肥っぽい副産物になり、微生物入りの土壌改良資材として再利用可能です!
・好気性のバチルス菌が含まれるため、米ぬかや落ち葉を混ぜたり土を攪拌するなど、適度に酸素を確保すれば、カルスNC-Rのような土壌再生効果・病気抑制効果を期待できます。
・塩分や油分の多いゴミは控えめにし、野菜くずや果物くず、コーヒーカスを中心に入れると品質が安定しやすいでしょう。
家庭で出る生ごみが、ただのゴミではなく“有機質たっぷりの資源”になるって、ちょっとワクワクしませんか? ぜひReencleを活用して、自前の「微生物入り土壌改良材」で安全&お得に土づくりを楽しんでみてくださいね!